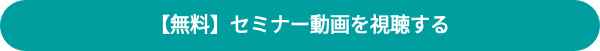医療業界のRPAツール自動化業務6選|病院での事例から学ぶ!自動化がもたらす効果と導入時の注意点
2025.07.30- 
医療現場では、診療報酬の請求業務や患者情報の管理など、日々膨大な事務作業が発生しています。
これらの業務を効率化し、医療スタッフが本来の業務に集中できる環境を整える手段として注目されているのがRPAです。
本記事では、医療機関におけるRPA導入の具体的な活用事例や、自動化による効果、そして導入時に注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
目次
- RPAとは?病院やクリニックなど医療業界で注目されている背景
- 医療機関のRPA導入メリット3つ
- 医療現場でのRPA業務自動化例(6選)
- 医療業界(病院)でのRPA導入事例/淀川キリスト教病院
- 医療業界におけるRPAツール導入の注意点
- まとめ
RPAとは?病院やクリニックなど医療業界で注目されている背景

近年、医療現場では人手不足や業務の効率化が大きな課題となっています。限られた人員で質の高い医療サービスを維持することが求められています。こうした状況下で、多くの病院やクリニックが注目しているのがRPAです。
RPAは、定型的な事務作業をソフトウェアロボットが自動で処理するツールであり、業務の効率化に加えて、人的ミスの削減や職員の負担軽減にもつながることから、医療業界での導入が急速に進んでいます。
RPAの特徴|医療業務との相性
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、あらかじめ決められた手順に従って、パソコン上で行われる定型作業を自動で実行するソフトウェアです。データ入力やファイル整理、定型フォーマットへの転記など、繰り返し発生する業務を人間に代わって実行できます。
医療現場では、診療報酬の請求や患者情報の管理、定期的な報告書の作成といった、ルール化された反復作業が数多く存在します。そのため、RPAとの相性は非常に良く、導入することで、職員の負担を軽減し、より重要な業務に集中できる環境を構築できます。
医療業界でRPAが注目されている理由
医療の現場では、質の高いサービスを提供するために多くの業務が発生していますが、慢性的な人手不足や業務量の増加により、スタッフへの負担が大きくなっています。特に医療事務においてはアナログな作業が多く残されており、効率化の余地が大きい分野です。こうした背景から、定型業務の自動化を実現するRPAが注目を集めています。
業界全体の背景(人手不足・業務量の増加)
日本の医療業界は、高齢化による患者数の増加や医療制度の複雑化により、日常業務が多様かつ煩雑になっています。加えて、医師・看護師・医療事務職員といった人材の確保が難しい状況であり、慢性的な人手不足が課題です。業務量は増える一方で、リソースが限られているため、業務効率の向上が急務となっており、その解決策の一つとしてRPA導入が進んでいます。
紙やデータ入力など根強く残るアナログ業務
病院やクリニックでは、患者情報の紙ベースでの管理、診療報酬の手入力処理、各種申請書類の作成など、手作業での業務が数多く残されています。これらの作業は時間と労力がかかるだけでなく、ヒューマンエラーの原因にもなりやすいのが現状です。こうしたルール化された反復作業はRPAとの相性が良く、導入することで大幅な省力化と業務の正確性向上が期待できます。
医療機関のRPA導入メリット3つ

医療機関では、限られた人員の中で患者対応や事務処理を同時にこなす必要があり、日常的な業務負担は非常に大きいものとなっています。特に医療事務や診療報酬請求といった定型作業は、時間がかかる上にミスが許されない重要な業務です。
こうした背景から、業務の正確性と効率性を両立できるRPAの導入が、医療現場においても急速に進んでいます。本章では、RPA導入による主な3つのメリットを解説します。
手作業の削減による効率化
診療報酬の請求処理、患者情報の入力、外部提出用の統計作成など、医療機関には繰り返し発生する事務作業が数多く存在します。これらの業務は、ルールが明確で手順が一定しているため、RPAによる自動化に非常に適しているのが特徴です。
RPAを活用することで、これまで手作業で行っていた処理を短時間で正確に完了でき、医療事務スタッフの作業時間を大幅に削減できます。結果として、病院全体の業務効率が向上し、より質の高い医療サービスの提供につながるでしょう。
限られた人材の有効活用
医療現場では慢性的な人手不足が大きな課題となっており、医療従事者が本来の専門業務以外にも事務作業を抱えるケースが少なくありません。RPAを導入すれば、単純な入力や集計といった作業から職員を解放し、看護や診療支援など、より専門的で人の判断が必要な業務に集中することが可能です。限られた人材をより効果的に活用できる体制を構築することは、医療機関のサービス品質や職員の満足度向上にもつながります。
人為的ミスの防止
医療現場では、患者情報や診療報酬に関わるミスが医療事故や請求トラブルにつながる可能性があり、業務の正確性が非常に重要です。RPAは、決められたルールに沿って機械的に作業を行うため、疲労や注意力の低下によって起こる入力ミスや計算ミスを防ぐ効果が期待できます。
特に、診療報酬の請求処理などミスが許されない業務では、RPAによる自動処理がリスク軽減に大きく貢献するでしょう。
医療現場でのRPA業務自動化例(6選)
%E3%81%AE%E7%94%BB%E5%83%8F.png?width=760&height=399&name=%E5%8C%BB%E7%99%82%E7%8F%BE%E5%A0%B4%E3%81%A7%E3%81%AERPA%E6%A5%AD%E5%8B%99%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8C%96%E4%BE%8B(6%E9%81%B8)%E3%81%AE%E7%94%BB%E5%83%8F.png)
医療現場では、診療や看護の合間に多くの事務作業が発生しており、医療従事者の業務負担を大きくしています。特に、データの入力や転記、帳票の作成といった定型的な作業は、人的ミスのリスクや時間的コストを伴うため、自動化の対象として非常に適しているでしょう。
本章では、医療機関で実際にRPA化が進められている代表的な業務を6つ取り上げ、具体的な手順と効率化のポイントを解説します。
RPA化① 電子カルテデータの転記
医療現場では、患者の診療情報や検査結果を電子カルテに入力し、それをもとに紹介状や診療情報提供書、院内の共有書類を作成する作業が頻繁に行われています。従来は、医師や事務スタッフがカルテを開き、該当情報を確認した上で、別の文書作成ソフトに手入力やコピー&ペーストで転記していました。
RPAを活用すれば、電子カルテ上の必要な項目(診療日、診断名、処方情報など)を自動的に抽出し、指定のフォーマットに転記できます。手間と時間を削減できるだけでなく、転記ミスの防止にもつながります。
RPA化② レセプト作成・点検業務の自動化
診療報酬請求に必要なレセプトの作成は、各診療行為に対して適切な点数や診療報酬コードを割り当てる複雑な業務であり、月末月初には医療事務に大きな負担がかかります。通常は、診療データを確認しながら請求データを作成・点検し、エラーがないか何度もチェックを行うケースが多いです。
RPAを導入することで、カルテ情報をもとに自動でレセプトの下書きを作成し、点検ルールに沿って不備や記載漏れのチェックも行うことが可能になります。作業のスピードと正確性が大きく向上し、再提出や差し戻しのリスクが軽減できるでしょう。
RPA化③ 検査結果のシステム入力・転記
血液検査や尿検査などの検体検査結果は、検査機器や検査室から出力されるレポートやCSVファイルなどをもとに、電子カルテなどの病院情報システムに入力する必要があります。従来は、検査技師や事務スタッフが一つひとつのデータを確認しながら手入力しており、入力ミスや作業遅延が課題となっていました。
RPAを活用すれば、検査データを自動的に読み取り、該当する患者データに紐づけて各システムに転記できます。入力作業にかかる時間を削減し、検査結果の迅速な共有が可能になります。
RPA化④ 薬剤在庫の管理・発注リストの作成
病院薬局では、薬剤の在庫確認や発注作業が定期的に行われています。通常は、在庫管理表や棚卸データを確認し、基準値を下回った薬剤を発注候補としてリストアップし、各メーカーや卸業者に手動で発注するという手順がとられます。
RPAを導入することで、在庫データベースをもとに定期的に在庫数をチェックし、あらかじめ設定した基準に従って自動的に発注リストを作成できます。さらに、発注システムとの連携により、発注処理まで自動化することも可能となり、薬剤師の作業負担の大幅な軽減につながります。
RPA化⑤ 問診表のデータ入力
初診や定期診察時に患者が記入する問診票は、紙で記入されたものを後から電子カルテに入力するか、タブレットで記入された内容を別のシステムに連携・移行する作業が必要になる場合があります。現場では、事務スタッフが一枚ずつ内容を確認しながら入力作業を行っており、対応の遅れや入力ミスが発生することもあるでしょう。
RPAを使えば、スキャンした問診票をOCRで読み取り、あるいはデジタル入力フォームの内容を抽出して、自動でカルテに反映させることが可能です。受付から診察までの流れがスムーズになり、待ち時間の短縮にもつながります。
RPA化⑥ 病床の管理
病院では、入院患者の数や退院予定に応じて病床の使用状況を常に把握し、空き病床の調整や病床稼働率の報告資料を作成する必要があります。現場では、各病棟から提出される表計算ファイルや紙資料をもとに手作業で集計し、管理部門が手動で一覧表を更新する必要があります。
RPAを導入すれば、各システムからリアルタイムでデータを収集し、自動で集計・可視化することが可能です。
また、OCR機能が搭載されているRPAツールであれば、紙資料のデータも読み取ることができ、さらに、AI-OCRと連携することで手書きや印刷文字の認識精度を高めることも可能です。これにより、紙ベースの情報も効率的に取り込み、病床の空き状況が常に最新の状態で確認できるため、入退院の調整や病棟間の連携がスムーズになります。
医療業界(病院)でのRPA導入事例/淀川キリスト教病院
%E3%81%A7%E3%81%AERPA%E5%B0%8E%E5%85%A5%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E6%B7%80%E5%B7%9D%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99%E7%97%85%E9%99%A2%E3%81%AE%E7%94%BB%E5%83%8F.png?width=760&height=399&name=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%A5%AD%E7%95%8C(%E7%97%85%E9%99%A2)%E3%81%A7%E3%81%AERPA%E5%B0%8E%E5%85%A5%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E6%B7%80%E5%B7%9D%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99%E7%97%85%E9%99%A2%E3%81%AE%E7%94%BB%E5%83%8F.png)
淀川キリスト教病院様のRPA導入は、コロナ禍による業務急増に対処するための施策として始まりました。綿密なトライアルと適切な部門主導体制、そしてベンダーであるヒューマンリソシアの技術支援を活用したことで、着実な効果をあげています。
具体的な導入事例について、詳しい内容をご紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
導入のきっかけ|医療現場の人員不足
新型コロナウイルスの感染拡大は、医療現場に大きな影響を与えました。
淀川キリスト教病院様においても、コロナ陽性者の発生による職員の欠勤や、濃厚接触者の自宅待機、さらには発熱外来の急増による現場支援など、人手不足が進んでいるような状況でした。
感染症対応に関する事務業務も膨大に増加し、限られた人員の中で日々の業務を維持することが大きな課題となっていました。
こうした背景から、業務効率化の必要性が高まる中で、RPA導入の検討が開始されます。以前より関心のあったRPAについて、ヒューマンリソシアより、NTTアドバンステクノロジ株式会社が提供するRPAツールのWinActorの提案を受け、60日間の無料トライアルから運用をスタートしました。
試験運用では、シナリオ作成や運用体制の整備、担当者の人選から効果検証に至るまで、ヒューマンリソシアの技術サポートを活用しながら着実に進行しました。業務改善への明確な効果が確認されたことで、本格導入へとつながっています。
自動化した業務
導入当初に自動化に着手したのは、新型コロナ対応に伴い急増した診療報酬請求関連の業務でした。コロナ患者の受け入れを行う医療機関であれば共通の課題といえますが、手順は単純な傾向があるものの件数が非常に多く、人的負荷の高い業務は、RPAによる自動化に非常に適していると判断し、導入されています。
当初はRPAの運用方法についてはほとんど知見がなく、不安も多いスタートでした。そうした中、60日間の無料トライアル期間中にヒューマンリソシアの技術サポートを活用し、初期段階から専門的な支援を受けながら運用体制を整備していきます。実際にヒューマンリソシアにて5つの業務でシナリオを作成し、現場での運用効果を確認していただきました。
初めてのRPA導入でも、信頼できるパートナーとともに進めることで、スムーズに運用を立ち上げることが可能です。次項では、実際に自動化した業務の一部をご紹介します。
①【月6時間削減】医事会計システムへの入力作業
導入初期に自動化した業務の一つが、「二類感染症患者入院診療加算」の入力作業です。これらは、コロナウイルスに感染、もしくは感染が疑われる入院患者に対して算定される加算であり、医事会計システムへの入力が必要となる業務です。
コロナ禍の影響により、入院前検査を必須としていたことから対象件数が急増し、月1,000〜1,500件ものデータをすべて手作業で入力していた状況でした。単純ながらも非常に負担の大きい業務であったため、RPAによる自動化を実施。WinActorを活用することで全件の入力作業を自動化し、月あたり約6時間分の作業時間を削減することに成功しました。
こうした定型かつ大量処理の業務は、RPAの効果を実感しやすい領域です。実際に取り組んでみて、業務効率だけでなく、職員の精神的負担の軽減にもつながっています。
②【月7時間削減】公費登録情報の入力作業
次に自動化を行ったのが、コロナ関連の公費登録業務です。新型コロナウイルス感染症に関しては、確定診断が出ていない段階でも、公費での医療費請求が必要となります。そのため、保険証の登録と同様に「公費番号」および「受給者番号」を医事会計システムへ登録する作業が発生していました。
この業務は患者ごとに入力が必要であり、対象者も多いため、手作業での処理に大きな負担がかかります。月に約1,500件もの登録業務が発生しており、対応にかかる時間は相当なものでした。
そこで、WinActorを用いて公費番号・受給者番号の入力作業を自動化することに成功。結果として、月あたり約7時間の作業時間を削減することができました。入力漏れやヒューマンエラーのリスクも低減でき、業務の正確性と効率が同時に向上しています。
③【年間6時間削減】 材料マスタの削除業務
定期的に発生する業務として、自社指定の材料マスタを物流システム上から削除する作業についてもRPAによる自動化を行いました。この業務は年に1〜2回程度の頻度で発生するもので、日常的な作業ではないものの、発生時には大量のデータを処理する必要があり、複数人で一気に対応していた業務です。
このような「頻度は低いが負荷の高い業務」は、どの業種・職種にも共通して存在しているのではないでしょうか。当院でも、業務の閑散期や職員の出勤状況を見ながら調整する必要があり、負担を予測しにくい作業でした。
そこで、WinActorを活用して該当するマスタ削除業務を完全自動化。従来は6時間程度かかっていた作業をゼロにすることができました。人的リソースに依存せず、実行タイミングも自由に設定できるため、職員の業務計画にも余裕が生まれ、作業の平準化にもつながっています。
課題解決に向けたRPA活用術
RPA導入を成功させるには、シナリオ作成に集中できる環境づくりが重要です。淀川キリスト教病院様では、RPA担当者のルーティン業務を先に自動化し、WinActor専用の日を設けてシナリオ作成を優先的に推進しています。
また、業務の細かいヒアリングを通じて自動化に適した業務を洗い出し、効率的な導入を図りました。さらに、導入初期は外部サポートを活用し、技術面での不安を解消。限られた人員でも成果を上げる体制を整えています。
医療現場の人員不足。課題解決に向けたRPA活用術/淀川キリスト教病院様
詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
医療業界におけるRPAツール導入の注意点

医療業界でRPAツールを導入する際には、一般企業とは異なる注意点が存在します。診療報酬や公費対応など、制度やルールが頻繁に変わる領域では、業務内容の変更に柔軟に対応できる体制づくりが不可欠です。
また、電子カルテや医事会計システムとの連携においては、個人情報を扱うことから、セキュリティリスクにも十分配慮する必要があります。この項目では、医療現場ならではの導入時の注意点と、それらを回避するための実践的なポイントについて解説します。
現場との連携不足による「使われないRPA」
医療現場においてRPAを導入する際、よくある失敗の一つが「現場で使われないRPA」が生まれてしまうことです。看護師、医療事務、検査技師などの実際の業務を担う現場スタッフと、情報システム部門や導入担当者との間で、課題認識や導入目的にズレが生じていると、構築した自動化シナリオが実際の業務フローに合わず、現場に定着しない事態になりかねません。
特に、「現場が求める業務プロセスを無視した自動化」は、業務改善どころか手間の増加を招き、RPAそのものへの不信感にもつながります。
こうした失敗を回避するには、導入前に必ず現場の担当者に丁寧なヒアリングを行い、業務内容や業務手順を正確に把握することが不可欠です。また、いきなり本格導入するのではなく、PoC(試験運用)から小さく始め、現場のフィードバックを得ながら段階的に展開していく方法が効果的といえるでしょう。
現場と一体となって進めることが、RPAが使われる仕組みを定着させ、真の業務改善につなげるための鍵となります。
「全部自動化」の落とし穴と段階的導入の重要性
RPA導入を検討する際、「どうせなら全部の業務を自動化したい」と考えるケースは少なくありません。しかし、導入初期からすべての業務を対象にしようとすると、設計や検証が複雑化し、結果的にRPAそのものが形骸化してしまうリスクが高まります。
特に医療業界のように、業務の幅が広く多職種が関わる現場では、複雑な業務を一気に置き換えようとするのは失敗の原因となるでしょう。
このような落とし穴を回避するためには、まずは定型的でシンプルな業務から自動化を始める「段階的導入」が重要です。定時で実行できる入力作業や、ルールが明確なチェック業務など、負荷が高いわりに判断が少ないタスクはRPAの効果が出やすい領域といえるでしょう。
小さな成功体験を積み重ねることで、現場スタッフにもRPAの利便性や効果が実感され、自然と導入が前向きに進むようになります。「できるところから少しずつ」が、RPA導入を成功に導く最大のポイントです。属人化を避けるため、複数人で保守できる体制を整えることも重要になります。
RPA開発・運用のブラックボックス化
RPAの開発・運用において注意すべき落とし穴のひとつが、「ブラックボックス化」です。特定の担当者だけがロボットの中身や仕組みを把握している状態になると、その担当者が異動・退職した際に、誰もメンテナンスできず、運用がストップするリスクがあります。
特に医療現場では、法改正や診療報酬制度の見直しなどが頻繁に発生するため、RPAシナリオの定期的な修正・更新が不可欠です。しかし、仕様が不透明な状態で放置されていると、いざという時に対応できなくなり、業務に支障をきたす恐れがあります。
こうしたリスクを防ぐには、シナリオの構成や処理内容を明確にドキュメント化し、誰が見ても理解できる状態にしておくことが重要です。また、担当者を限定せず、複数人で保守・運用を共有できる体制を整えることで、属人化を回避し、RPAの安定稼働と継続的な改善につなげることができます。
ブラックボックス化を防ぐ体制づくりが、RPAを長く使える仕組みに育てる第一歩です。
医療機関でのRPA活用におけるセキュリティリスクと対策
医療現場でRPAを導入する際は、セキュリティリスクの上昇に注意が必要です。
RPAはログイン処理やデータ取得の過程で、ID・パスワードやカルテ情報などを一時的にExcelファイルやプログラム内の変数に保持して処理を実施するケースがあります。
このような情報が漏洩すると、重大なインシデントにつながる可能性があるため、たとえば、以下のような基本的な対策を導入前から検討しておくことが重要です。
・RPA実行者の限定(誰でも実行できる状態にしない)
・実行ログの取得と定期チェック
・ID・パスワードの暗号化・安全な管理
・実行タイミングのルール化(業務時間外など)
医療分野では特に、患者の個人情報など取り扱いに細心の注意が必要な情報が多く含まれるため、RPAの導入にあたっては「効率化」だけでなく「安全性」にもしっかり目を向けることが大切です。
医療現場に合ったRPAツールの選定
RPAツールは多種多様に存在しますが、医療機関が導入する際には、業界特有の事情を踏まえた慎重な選定が必要です。特に注意したいのが、「現場のITリテラシー」と「既存システムとの連携性」です。
これらを考慮せずに選定してしまうと、「使いづらい」「運用負担が大きい」といった問題が発生し、せっかく導入しても現場に定着しないケースも少なくありません。
また、高機能なツールであっても、その設定や管理が複雑すぎると、導入・運用の段階で現場スタッフの負担が増大し、結果として業務効率化につながらない場合もあります。
こうした課題を避けるためには、医療機関への導入実績が豊富なツールや、ノーコード・ローコードで運用可能な製品を選ぶことが望ましいでしょう。さらに、導入支援から運用保守までを一貫してサポートしてくれるベンダーの存在も、導入成功の大きな要因になります。
現場にフィットするRPAを選ぶことで、業務効率化だけでなく、職員の働きやすさにも直結する結果が期待できるでしょう。
まとめ

本記事では、以下の内容についてご紹介しました。
・医療現場におけるRPA導入のメリットと効果
・RPA導入にあたっての現場連携と段階的な進め方の重要性
・医療業界特有の導入時の注意点とリスク管理
医療業界におけるRPA導入は、事務作業の効率化や人的ミスの削減に大きく貢献します。
本記事で紹介した実際の病院事例では、診療報酬請求や公費登録、在庫管理などの業務を自動化することで、
業務時間を大幅に削減し、職員の負担軽減につながっています。
ただし、導入時には現場との連携や段階的な導入、適切なツール選定が重要です。
RPAは業務改善の有効な手段ですが、現場に合った形で運用することが成功の鍵となります。
医療現場でのRPA導入は、現場との連携や導入プロセスで不安を感じることもあるかもしれません。
ヒューマンリソシアでは、豊富な実績を基に、貴社の状況に寄り添ったサポートを導入から運用まで一貫して提供いたします。
ぜひお気軽にご相談ください。
【よくあるご質問】
医療現場におけるRPA活用とは
Q. 医療現場で活用されているRPAとは何ですか?
A: RPAとは、RPA(Robotic Process Automation)の略で、パソコン上で行われる定型的な事務作業をソフトウェアロボットが自動で処理するツールです。医療現場では、診療報酬の請求や患者情報の管理、定期的な報告書の作成といった、ルール化された反復作業に活用され、業務の効率化、人的ミスの削減、職員の負担軽減に貢献します。
医療機関がRPAを導入するメリット
Q. 医療機関がRPAを導入するメリットは何ですか?
A: 手作業の削減による効率化: 診療報酬の請求処理、患者情報の入力、外部提出用の統計作成など、繰り返し発生する事務作業をRPAが短時間で正確に完了させ、医療事務スタッフの作業時間を大幅に削減できます。
A: 限られた人材の有効活用: RPAで単純な入力や集計作業を自動化することで、医療従事者は看護や診療支援など、より専門的で人の判断が必要な業務に集中できるようになります。
A: 人為的ミスの防止: RPAは決められたルールに沿って機械的に作業を行うため、疲労や注意力の低下によって起こる入力ミスや計算ミスを防ぐ効果が期待できます。特に、診療報酬の請求処理などミスが許されない業務でのリスク軽減に貢献します。
医療現場におけるRPAの主な活用業務
Q. 医療現場でRPAにより自動化できる業務にはどのようなものがありますか?
A: 電子カルテデータの転記: 電子カルテ上の必要な項目を自動抽出し、紹介状や診療情報提供書、院内共有書類などの指定フォーマットに転記します。
A: レセプト作成・点検業務の自動化: カルテ情報をもとにレセプトの下書きを自動作成し、点検ルールに沿って不備や記載漏れをチェックします。
A: 検査結果のシステム入力・転記: 検査データを自動的に読み取り、該当する患者データに紐づけて各システムに転記します。
A: 薬剤在庫の管理・発注リストの作成: 在庫データベースをもとに定期的に在庫数をチェックし、設定基準に従って自動的に発注リストを作成、発注処理まで自動化できます。
A: 問診票のデータ入力: スキャンした問診票をOCRで読み取り、またはデジタル入力フォームの内容を抽出して、自動でカルテに反映させます。
A: 病床の管理: 各システムからリアルタイムでデータを収集し、病床の使用状況を自動で集計・可視化し、入退院の調整や病棟間の連携をスムーズにします。
医療現場でのRPA導入時の注意点
Q. 医療現場でRPAを導入する際の注意点は何ですか?
A: 現場との連携不足による「使われないRPA」: 実際の業務を担う現場スタッフと導入担当者の間で課題認識や目的にズレがあると、自動化シナリオが実際の業務フローに合わず、現場に定着しない可能性があります。導入前の丁寧なヒアリングとPoC(試験運用)を通じた段階的導入が重要です。
A: 「全部自動化」の落とし穴と段階的導入の重要性: 初期からすべての業務を対象にすると、設計や検証が複雑化し失敗のリスクが高まります。まずは定型的でシンプルな業務から自動化を始め、小さな成功体験を積み重ねることが重要です。
A: RPA開発・運用のブラックボックス化: 特定の担当者だけがRPAの仕組みを把握していると、担当者が異動・退職した際にメンテナンスができなくなるリスクがあります。シナリオのドキュメント化と複数人での保守・運用共有体制の整備が重要です。
A: 医療機関でのRPA活用におけるセキュリティリスクと対策: 患者の個人情報など機密性の高い情報を扱うため、RPA実行者の限定、実行ログの取得と定期チェック、ID・パスワードの暗号化・安全な管理といった基本的なセキュリティ対策が不可欠です。
A: 医療現場に合ったRPAツールの選定: 現場のITリテラシーや既存システムとの連携性を考慮し、医療機関への導入実績が豊富で、ノーコード・ローコードで運用可能なツールを選ぶことが望ましいです。また、導入支援から運用保守までを一貫してサポートしてくれるベンダーの存在も重要です。
医療機関でのRPA導入事例
Q. 医療機関でのRPA導入事例はありますか?
A: はい、淀川キリスト教病院様での導入事例があります。コロナ禍による業務急増に対応するためRPAを導入し、以下の業務を自動化しました。
- 医事会計システムへの入力作業: 「二類感染症患者入院診療加算」の入力作業を自動化し、月あたり約6時間の作業時間を削減しました。
- 公費登録情報の入力作業: コロナ関連の公費登録業務を自動化し、月あたり約7時間の作業時間を削減しました。
- 材料マスタの削除業務: 年に1〜2回発生する材料マスタの削除業務を完全自動化し、従来6時間程度かかっていた作業をゼロにしました。
本コラム内容について
各コラムの内容は、執筆時点での情報を元にしています。
製品バージョンアップなどにより、最新ではない場合がありますので、最新の情報は、各社の公式サイトなどを参考にすることをおすすめいたします。
各コラムの内容は、利用することによって生じたあらゆる不利益または損害に対して、
弊社では一切責任を負いかねます。
一つの参考としていただき、利用いただく際は、各社のルール・状況等に則りご活用いただけますと
幸いです。
※「WinActor®」は、NTTアドバンステクノロジ株式会社の登録商標です。